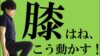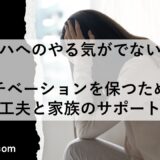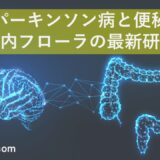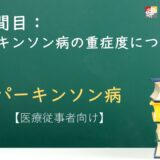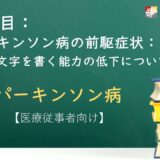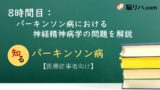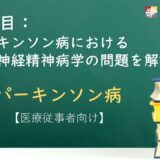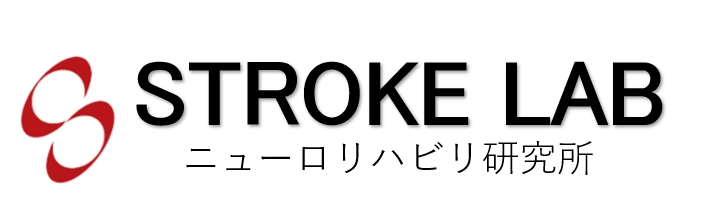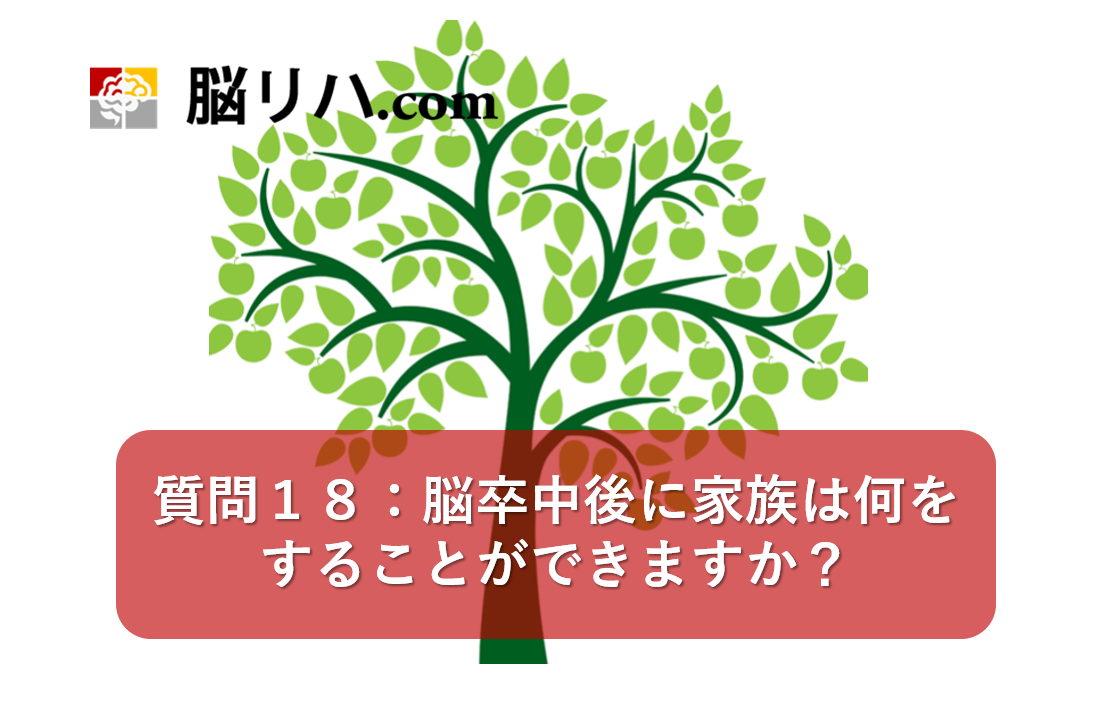
Facebook メルマガ登録にて定期的に最新情報を受け取れます。
質問18:脳卒中後に家族は何をすることができますか?
専門家からの回答
脳卒中発症後、感情も高まっている中、物事はどんどん進行していきます。そして、それは誤解や不安・不確実性を生んでしまう事もあります。理想とされる形は、どなたか一人が先導となり、家族が構造化されたツリーとなることです。そうすれば、医療従事者は、先導の方を通して、多くの情報をやり取りし、家族間・医療者と各家族との間でも行き違いなどが生まれづらくなります。
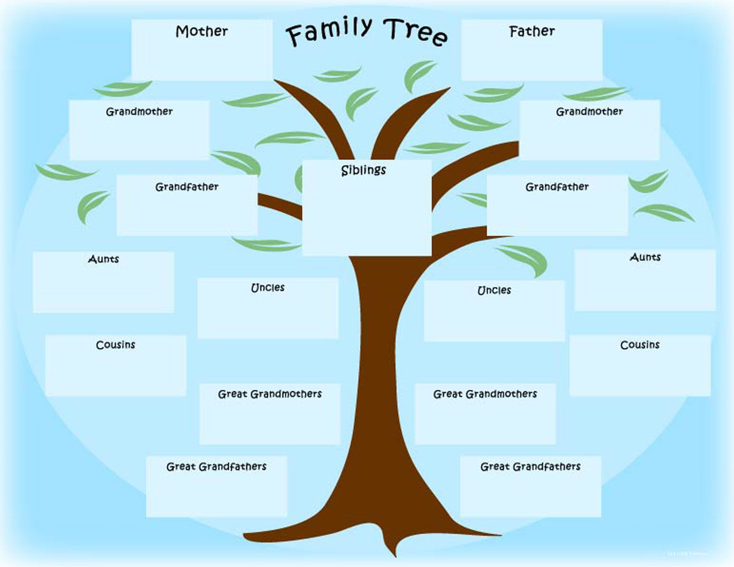
1人または2人の定めた家族が中心となる明確なコミュニケーションは、家族が入手し行動することができる情報の力を最大にする事に役立ち、緊急事態があっても迅速に対応することができます。
同じ家族でも様々な御本人との向き合い方があります。ただ、そばにいるだけで励ましとなったり動機づけになる方、家族の先陣を切って物事を進めるリーダーとなる方、日頃のストレスを晴らすかのように他愛もない話をし合う方・・。

脳卒中後の回復は進んでいきます。ずっとベッドで寝ている必要はありません。その場その場で、出来る事が変わっているかもしれません。リハビリスタッフや看護スタッフに情報をもらい、時には車椅子・歩行補助の指導など受け、今できる能力で関わってあげて下さい。話だけでなく、体で御本人の回復を感じてあげて下さい。実際、家に帰った時のイメージなどもつきやすくなると思います。
家族は、脳卒中の回復における感情的ケア・長年の関りからの気兼ねない本人への教育・リハビリと回復にとって大切な全てを行うことが出来ます。患者・家族・医療従事者は、回復を最大限にするための共通の目標に向かってチームとして働く必要があります。

回復をサポートするチーム
医師と看護師が病院の医療チームの一員であることは承知していると思いますが、他にも多くの人が関わっています。
理学療法士PT:脳卒中後の身体機能面に対する訓練に重きをおいて関わります。身の回り動作や歩行などの移動能力を高め、日常生活の再獲得を図ります。
作業療法士OT:脳卒中後の日常生活(トイレ・入浴・家事など)に対する練習や手作業などを通して手指機能の改善などを促します。
PTとOTは目標によっては、双方の介入時間で共に同じような練習を集中的に行ったり、または分担して練習したり、相談の下ご本人様の必要性に応じて介入している事が多いです。
言語聴覚士ST:脳卒中後の言語障害・嚥下障害(食事)・高次脳機能障害などに対して訓練を行います。
栄養士:脳卒中後の回復を栄養面からサポートします。必要な栄養素を使い健康的な食事を取れるようにします。
薬剤師:薬を管理し、副作用や相互作用を監視します。
その他、多くの方が関わっています。脳卒中回復チームのメンバーは家族です。
脳卒中の程度や年齢などはコントロールすることはできませんが、より良く回復するためのモチベーションや意思決定・行動をコントロールできます。神経可塑性に伴う回復は御自身が持ち合わせています。
回復は大変な道のりですが、どなたか鍵となるご家族が、医療チームとコミュニケーションを密にしてその情報をご本人や他のご家族と共有できるとご本人の回復における心身の支援がスムーズに行くと思われます。
執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表
・国家資格(作業療法士)取得
・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務
・海外で3年に渡り徒手研修修了
・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

国家資格(作業療法士取得)
順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務後,
御茶ノ水でリハビリ施設設立 7年目
YouTube2チャンネル登録計40000人越え
アマゾン理学療法1位単著「脳卒中の動作分析」他
「近代ボバース概念」「エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション」など3冊翻訳.
————————————————————
〒113-0033 文京区本郷2-8-1 寿山堂ビル3階
ニューロリハビリ研究所 STROKE LAB
電話番号:03-6887-5263
メールアドレス:t.kaneko@stroke-lab.com
TwitterやYouTubeなどはアイコンをクリック↓↓↓