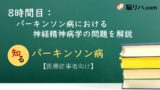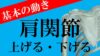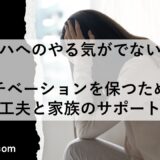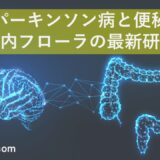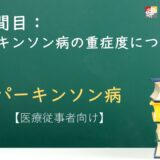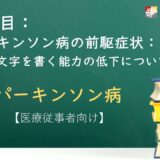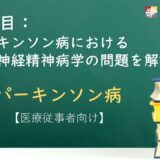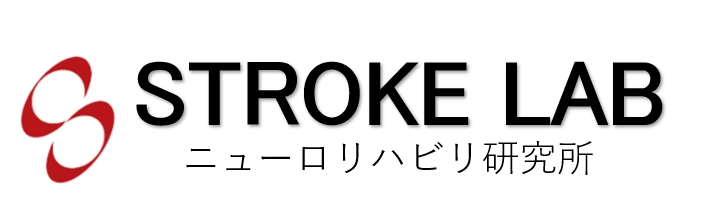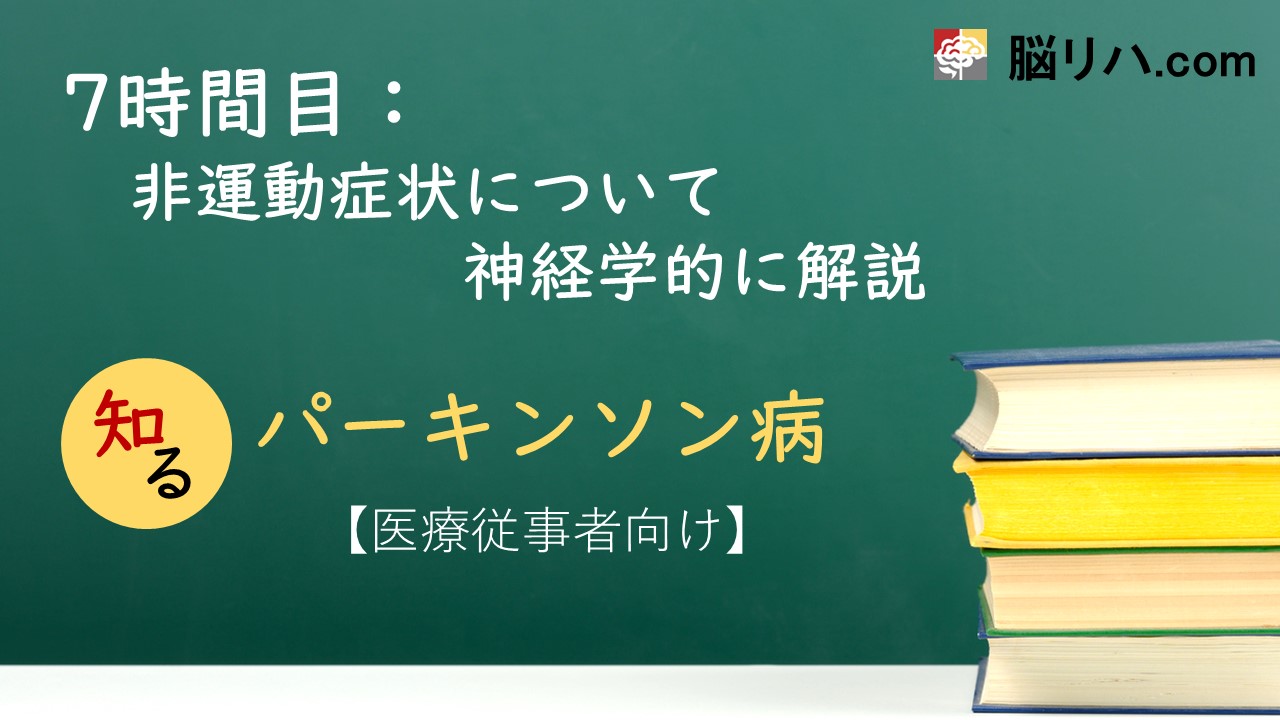
Facebook メルマガ登録にて定期的に最新情報を受け取れます。
7時間目:非運動症状について
パーキンソン病は古くから「運動症状」が主たる病態と考えられてきました。しかし近年では「非運動症状(Non-motor symptoms)」の重要性が広く認識され、これらの症状が生活の質(QOL)低下に大きく寄与することが明らかになっています。
これを「氷山モデル」として考えます。すなわち、海面上に突き出ている氷山の“目に見える部分”が振戦(震え)や筋固縮、無動・寡動、姿勢反射障害といった運動症状である一方、海面下に隠れている遥かに大きな部分が、非運動症状の多彩な病態であると考えられています。

非運動症状の多彩な臨床像
パーキンソン病患者の多くは、運動症状がはっきりと表出する時点より前に、さまざまな非運動症状を経験している可能性があります。これらは「前駆症状(prodromal symptoms)」とも呼ばれ、嗅覚障害・便秘・レム睡眠行動障害(RBD)・抑うつ・不安 などが代表的です。
さらに、病気の進行に伴い、自律神経症状(起立性低血圧、排尿障害、発汗異常、便秘など)や認知機能障害、精神症状(幻視、妄想、アパシーなど)が深刻化し、患者の生活を制限する大きな要因となります。最近の研究では、これら非運動症状が運動症状以上に患者のQOLを阻害するとの報告も増えています
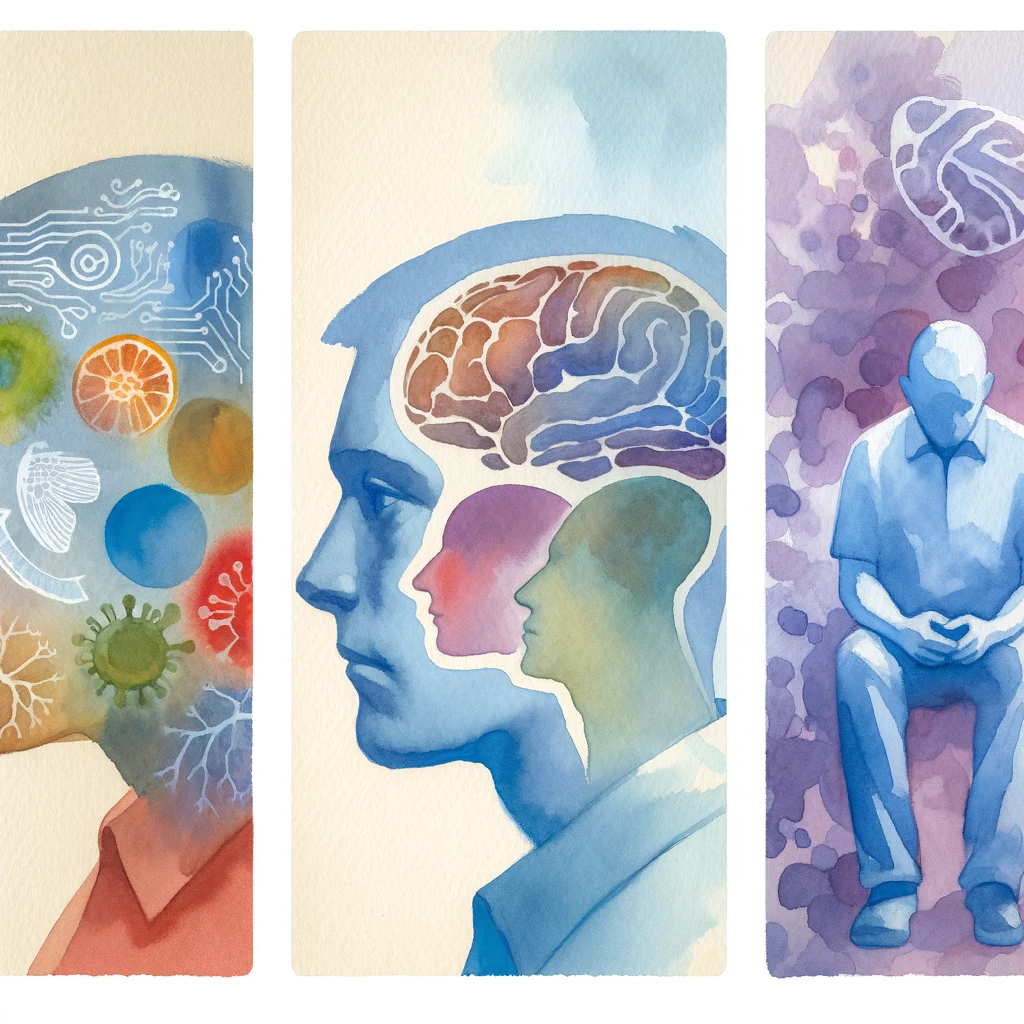
神経伝達物質の多面的な枯渇:ドーパミンだけではない病態
非運動症状が生じる背景として、「ドーパミン(DA)系の変性」だけでは説明しきれない多領域・多神経伝達物質の関与が示唆されています。具体的には、以下のような神経伝達物質が低下し、それぞれが特有の非運動症状の発現や進行に寄与します。
●セロトニン(5-HT)
うつ、不安、睡眠障害などに深く関与。縫線核(raphe nucleus)の変性による枯渇が指摘されており、前駆期から精神症状を伴うケースが多く報告されています。
●ノルアドレナリン(NA)
覚醒レベルの制御や自律神経系の調整に寄与。青斑核(locus coeruleus)の変性による欠乏が起立性低血圧や自律神経症状の原因になり得ると考えられています。
●アセチルコリン(ACh)
中枢神経系では記憶や学習機能に密接に関与しており、これが低下すると認知症状や幻視が生じやすくなります。
●その他の神経伝達物質
グルタミン酸やGABA、ドーパミン以外のモノアミン類も含めて多彩なネットワークが影響を受けている可能性があります。
これらの変化はパーキンソン病におけるαシヌクレイン(α-synuclein)を中心とする病理学的変化が、ドーパミン作動性ニューロン以外にも波及している事実と一致します

病理学的背景:脳幹核からはじまる変性の広がり
近年の病理学的研究(Braakらによる病期分類など)によれば、パーキンソン病の変性は黒質緻密部(Substantia nigra pars compacta)にとどまらず、以下のような脳領域における神経変性を認めるケースが多いことが示唆されています。
縫線核(raphe nucleus) : セロトニン産生ニューロンが集積
青斑核(locus coeruleus): ノルアドレナリン産生ニューロンが集積
背側迷走神経核(dorsal motor nucleus of the vagus): 自律神経を司る核
シロオビ核(nucleus basalis of Meynert): アセチルコリン産生ニューロンが集積
これらの広範囲な変性が、非運動症状の発症および悪化に大きく寄与すると考えられています。初期には脳幹部や嗅球などから病理変化が始まり、徐々に上行して大脳皮質へ波及するため、運動症状の出現前に前駆症状としての非運動症状を認めることが多く報告されています

臨床的意義:非運動症状へのアプローチ
早期発見と前駆症状の評価
非運動症状の存在は、パーキンソン病の早期診断や治療のタイミングを検討するうえで重要な指標となります。特に嗅覚障害、RBD、うつ、不安などに着目することで、将来的なパーキンソン病の発症リスクを評価できる可能性があります
包括的な治療戦略の必要性
従来の治療はドーパミン補充療法(L-DOPAやドパミンアゴニスト)を主軸としてきましたが、セロトニン・ノルアドレナリン・アセチルコリンなど多様な系へのアプローチも考慮され始めています。例として、
・抗コリン薬による精神症状や認知機能の維持
・SSRI/SNRIなどを用いた抑うつ・不安症状の改善
・便秘対策にはプロバイオティクスや下剤の適切な活用
・起立性低血圧に対する昇圧薬や生活指導
といった多職種連携での治療やサポートが求められます

QOL向上とケアの最適化
非運動症状への適切な対応は、患者のQOL向上に直結します。認知機能障害、精神症状、自律神経症状などを総合的に評価し、必要に応じて専門医(精神科・心療内科・泌尿器科など)と連携したマネジメントを行うことが重要です。

まとめ
パーキンソン病は“運動症状”という氷山の一角だけでなく、水面下に存在する多彩な“非運動症状”こそが患者の長期的なケアにおける大きな課題といえます。脳内のドーパミン枯渇だけでなく、セロトニン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなど複数の神経伝達物質が長期的に変性・低下するため、非運動症状は多面的かつ進行性に悪化し得ます。
最新の知見をもとに、早期発見、的確な評価、多様な治療戦略の検討が欠かせません。医療従事者がこの病態生理を理解し、非運動症状を含めた包括的なアプローチを実践していくことが、パーキンソン病患者のQOLと治療成績を高めるうえで最も重要です。

引用・参考文献
1.Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH. Non-motor symptoms of Parkinson’s disease: diagnosis and management. Lancet Neurol. 2006;5(3):235-245.
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70373-8
2.Olanow CW, Stern MB, Sethi K. The scientific and clinical basis for the treatment of Parkinson disease. Neurology. 2009;72(21 Suppl 4):S1-S136.
https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181a1d44c
3.Spillantini MG, Schmidt ML, et al. Alpha-synuclein in Lewy bodies. Nature. 1997;388(6645):839-840.
https://doi.org/10.1038/42166
4.Braak H, Tredici KD, Rüb U, et al. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson’s disease. Neurobiol Aging. 2003;24(2):197-211.
https://doi.org/10.1016/S0197-4580(02)00065-9
5.Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease. Mov Disord. 2015;30(12):1591-1601.
https://doi.org/10.1002/mds.26424
退院後のリハビリは STROKE LABへ
当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆、2024年に医学書院より発売された「脳の機能解剖とリハビリテーション」から以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。
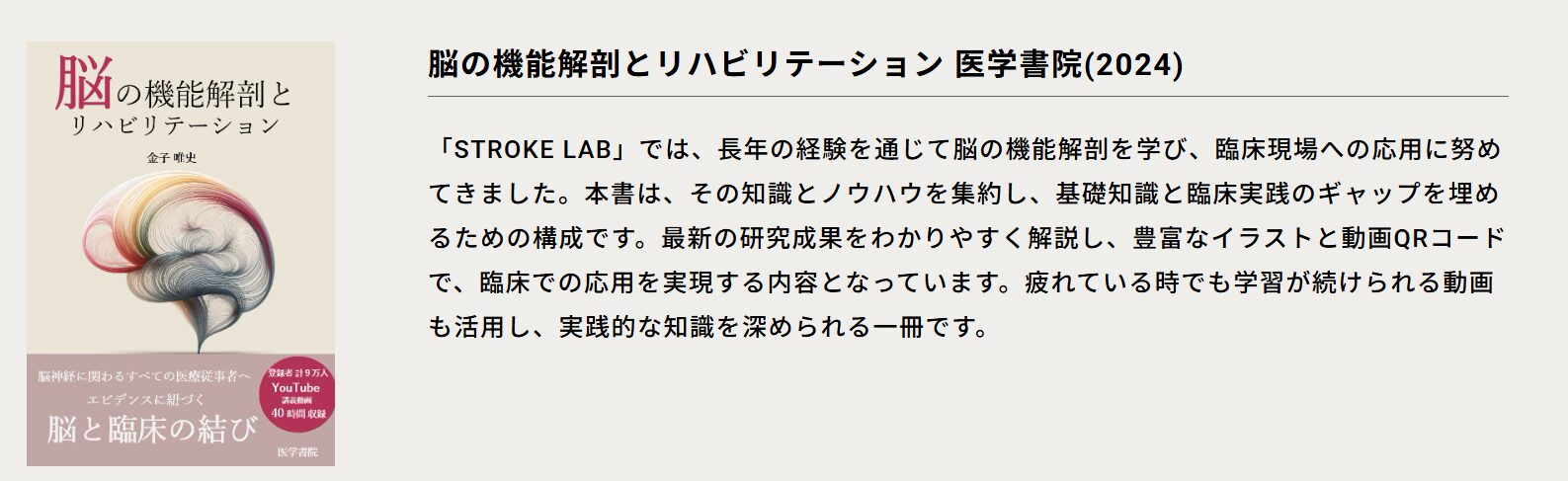

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

国家資格(作業療法士取得)
順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務後,
御茶ノ水でリハビリ施設設立 7年目
YouTube2チャンネル登録計40000人越え
アマゾン理学療法1位単著「脳卒中の動作分析」他
「近代ボバース概念」「エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション」など3冊翻訳.
————————————————————
〒113-0033 文京区本郷2-8-1 寿山堂ビル3階
ニューロリハビリ研究所 STROKE LAB
電話番号:03-6887-5263
メールアドレス:t.kaneko@stroke-lab.com
TwitterやYouTubeなどはアイコンをクリック↓↓↓